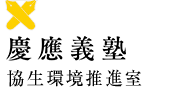交差する空間、対話する空間
「居場所」を辞書で引くと「その人が身を落ち着けていられる場所」1 とあります。多様性を大事にする大学において、それはどのような空間なのでしょうか。「生きづらさ」を生む社会の構造とそれに抗う構えから考えてみます。
「インターセクショナリティ」という概念から始めましょう。私たちの社会にはジェンダーをはじめ、人種、エスニシティ、階級、ディサビリティ、年齢、セクシュアリティなど、さまざまな差異があり、インターセクショナリティとは、そうした差異が複雑に交差して構造的な抑圧や不平等を生み出していることを理解し、変革を可能にするための考え方です。このことばを最初に使用したのは、アメリカの法学者で活動家のキンバリー・クレンショウでした。1989年に発表した論文「人種と性の交差を周辺から中心に」2 において、差別を交差点(intersection)のイメージに重ね合わせて説明しています。事故が交差点上で起こるとき、それは複数の方向から来る車によって引き起こされる場合もあれば、ときには全方向からかもしれません。論文でクレンショウが明らかにしたのは、ジェンダーや人種や階級やそれ以外のアイデンティティがいくつか重なって、複数の形で周辺化される人は、車が行きかう「交差点」に立っているようなものだということです。社会からいくつもの方法で疎外されている人は、車を何台も避けなければならず、交差点に立つ危険が増すことを指摘しています。
クレンショウのイメージが重要であるのは、差別の複合性――複数の差別に晒されている――ばかりでなく、それらの差別が交差していることから生じる抑圧の構造をも明らかにするからです。「構造的差別(institutional racism)」ということばを聞いたことがあるでしょうか。インスティテューショナルには、「組織的な」、「慣習化された」という意味がありますから、差別が社会に内包されているということだと理解できます。だからこそ、根底から変革をする必要があるわけです。もし、身近な風景を思い浮かべ多様性を尊重する社会が実現しつつあると感じているとすれば、より遠くの周縁にまで目を向けてください。これまで気づくことのなかった、複合的な困難を抱えている人が視野に入るはずです。
インターセクショナリティの考え方を深く理解すると、私たちは最初に挙げた、人種、エスニシティ、階級、ディサビリティ、年齢、セクシュアリティといった差異に限らず、様々な生きづらさを抱えている人びとの存在に気づきます。そして、危険が交差する交差点ではなく、誰もが安心できるような居所が必要であることもわかります。人の抱える生きづらさは、複合的かもしれませんし、複雑かもしれません。そういった心の声を伝えられる空間とはどの様なところでしょうか。クレンショウと同時代を生きた詩人マヤ・アンジェロウは、私たち誰もが「疑念をいだかれず、有りのままでいられる安全な場所を切望している」と語りました3 。問われることも探られることも咎められることもなく、静かにくつろげる、少し心を開いてみても、対話を試してみても構わない、緩やかに繋がれる協生空間が理想でしょうか。
2025年5月、「協生ステーションarcoíris」がオープンします。
1 『新明解 国語辞典』 第七版
2 Kimberlé Crenshaw, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics" (University of Chicago Legal Forum, 1989年)
3 Maya Angelou, All God's Children Need Traveling Shoes (1986年)
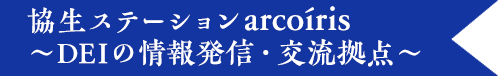
ジェンダー、セクシュアリティ、障害、人種、文化など、私たちの間に存在する様々な違いを"違い"ではなく、"個性"として尊重し、理解しあうことを目指した情報発信と交流の場です。
自分らしさを大切にしながら、それぞれが自由に、そして尊重されながら過ごせる場所
‥‥それが"協生ステーションarcoíris"です。
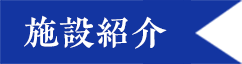
塾生および教職員が誰でも安心して利用できる安心・安全な空間です。静かに過ごしたいときには読書や勉強に集中する場として、そして話したい・相談したいときには、常駐するコーディネーターと対話することができます。



arcoíris(アルコイリス)スペイン語で「虹」を意味します。また希望、未来、多様性、架け橋といったポジティブな意味を持ちます。
「iris(アイリス)」は、ギリシア神話の虹の女神、アヤメ科の花の名前、花言葉は「希望」「よい便り」。
異なる色が調和して一つの美しい形を成すように、多様な個性が共に生き、響きあう社会の実現に向けて、「協生ステーションarcoiris」は、塾生・教職員みなさんの居場所となることを願っています。
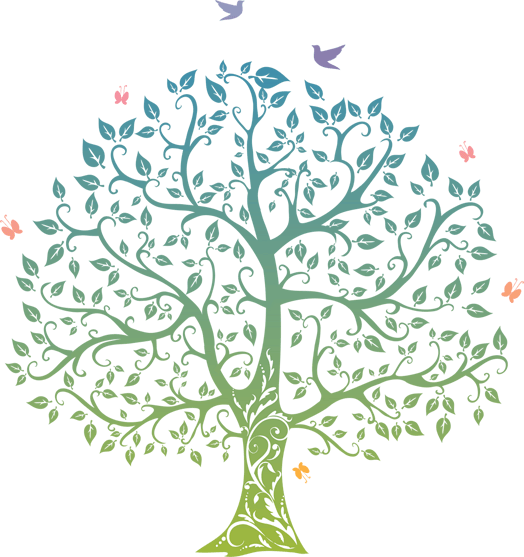
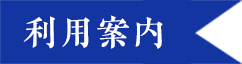
場所:慶應義塾 三田キャンパス
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
三田インフォメーションプラザ2階 MAP
開室時間:火・木・金(11:30-16:00)
Lunch Time(11:30-13:30)
※開室日時は変更になる場合があります。
最新の情報は 開室カレンダー をご確認ください。
利用できる人:塾生、教職員
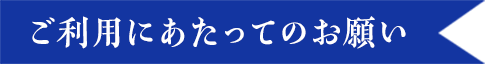
快適で安心できる空間を保つために、以下の点にご協力をお願いします。
-
1.静かなご利用を
周囲の方が安心して過ごせるよう、大きな声での会話や通話はご遠慮ください。
-
2.長時間の占有はお控えください
譲り合いの気持ちを大切に。必要な方がスムーズに使えるようご協力をお願いします。
-
3.指定の時間以外の飲食はお控えください
(特別な事情がある場合を除く) -
4.使用後は元の状態に戻してください
椅子や備品などは、使う前の状態に戻していただけると助かります。
-
5.プライバシーの尊重を
他の利用者への干渉は控え、お互いに安心して過ごせる空間を大切にしましょう。

-
・個別相談
ジェンダーやセクシュアリティ、生活、キャリア、就職・就労に関する個別相談を受け付けています。「誰にも相談できずに悩んでいる」「自分らしい生き方や働き方を見つけたい」そんな気持ちを、安心して話せる場です。相談内容は秘密厳守。一人で抱え込まず、まずは話すことから始めてみませんか。あなたの気持ちに寄り添い、一緒に考える時間を大切にしています。
※個別相談についてはこちらをご覧ください。
-
・学内連携
ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの実現を推進する拠点として、学内の関連組織や各種相談窓口と密に連携し、全塾的な支援体制を構築していきます。
-
・誰もが安心して過ごせる環境づくり
誰もが不安なく過ごせるキャンパスを目指して、学内の環境や制度のバリアフリー化を積極的に推進します。見えづらいバリアにも目を向け、「誰一人取り残されない」環境づくりを進めて行きます。
-
・啓発・情報発信
「協生環境推進ウィーク」などを中心に、ダイバーシティへの理解を深めるためのイベントや企画を行います。ルームでは不定期にワークショップや勉強会を開催します。